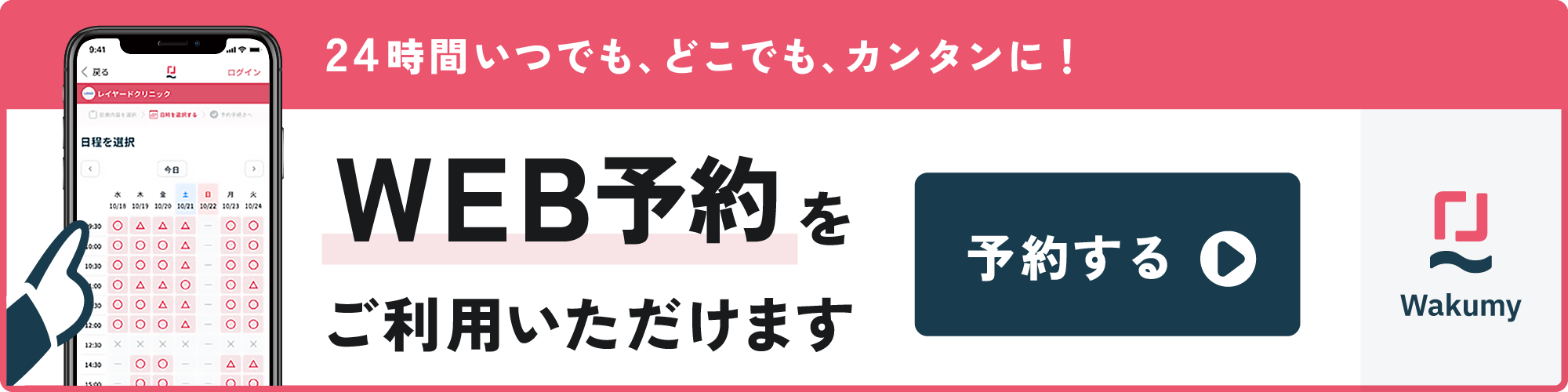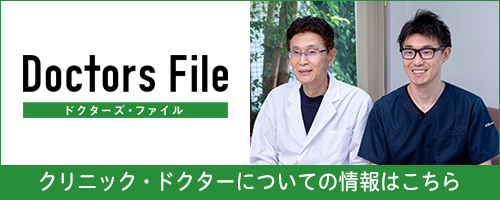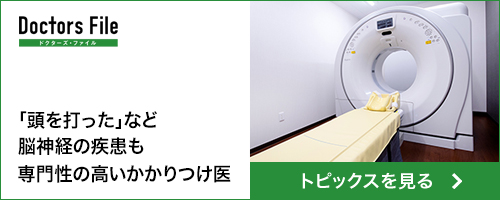肺炎
肺炎は市中肺炎(在宅肺炎)と院内肺炎(病院入院中)に大きく分けられます。市中肺炎は通常の社会生活を営んでいる人にみられる肺炎です。一方、院内肺炎は入院している患者さんが基礎疾患(糖尿病、がん、外科的手術後、エイズなど)や治療(副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤など)により感染しやすくなり、病院内で感染した肺炎です。日本人の原因別死亡率では、肺炎は4位に位置しており、肺炎で死亡する人の92%は65歳以上の高齢者です。
ここでは感染症としての肺炎を扱い、他の原因による肺炎、原因不明の間質性肺炎である突発性間質性肺炎については触れていません。
肺炎の原因
肺炎は原因となる病原体などの種類により、細菌性肺炎、非定型肺炎(マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎)、レジオネラ肺炎、ウイルス性肺炎、真菌性肺炎、寄生虫肺炎などに分類されます。
病理形態学的な分類では、肺炎は大葉性肺炎(肺炎球菌、クレブシエラなど)と気管支肺炎(黄色ブドウ球菌、インフルエンザ菌など)そして肺胞隔壁に病変の主な部位がある間質性肺炎(ウイルスなど)に分かれます。
-
細菌性肺炎
この肺炎は最も頻度の高いものです。かぜ症候群に引き続き起こる市中肺炎では、肺炎球菌、インフルエンザ菌、連鎖球菌によるものが多くなっています。 慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎、気管支拡張症などをもつ患者さんには、肺炎球菌、インフルエンザ菌(インフルエンザウイルスとは異なります)、モラキセラ(ブランハメラ)、緑膿菌(りょくのうきん)による肺炎の頻度が高くなっています。
院内肺炎では、抗菌薬が長期に使用されていると、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)などの耐性菌の頻度が高くなります。 原因菌別の特徴は以下のようになっています。
- 肺炎球菌性肺炎:市中肺炎の起炎菌として頻度が最も高いです。ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)が増加しており問題になっています。肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)が有効です。
- インフルエンザ菌性肺炎:慢性気道感染患者の気管支肺炎としてみられます。βラクタマーゼ非産生アンピシリン耐性インフルエンザ菌(BLNARインフルエンザ菌)が増えていて、抗菌剤の選択が重要になってきます。
- 黄色ブドウ球菌性肺炎:気管支(巣状)肺炎の代表的な原因菌。院内感染でのMRSAが問題になっています。
- レジオネラ肺炎:循環型の風呂に集団発生がみられ、問題になりました。
- クレブシエラ肺炎:高齢者、アルコール多飲者に発症しやすくなります。
- 緑膿菌性肺炎:院内肺炎の代表的菌種で、化学療法歴の長い症例では、緑膿菌の持続感染がみられます。
マイコプラズマ肺炎
非定型肺炎の代表です。若年者層に比較的多く、頑固な乾いた咳がみられます。若年者の肺炎を見た場合には、まずマイコプラズマ肺炎を疑います。診断のためにはマイコプラズマ抗体価や白血球数、CRPなどを測定します。
クラミジア肺炎
非定型肺炎の形をとり、鳥類(オーム、インコなど)との接触歴のある人に多く、高熱、乾いた咳、頭痛、筋肉痛などがみられます。
ウイルス性肺炎
原因ウイルスは、インフルエンザウイルスがその代表です。これに引き続く細菌の二次感染(肺炎球菌、インフルエンザ菌)による肺炎(インフルエンザ後肺炎)がよく見られます。
肺炎の症状
発熱、全身倦怠感、食欲不振などの全身症状と、咳、痰、胸痛、呼吸困難などの呼吸器症状がみられます。
肺炎球菌性肺炎では悪寒、発熱、頭痛、咳、痰を5大症候とし、そのほか頭痛、全身倦怠感、食欲不振などの全身症状がみられます。高齢者では発熱がはっきりしない場合もありますので、注意が必要です。
肺炎の検査と診断
検査所見としては、白血球増加、CRP高値などの炎症反応が特徴的です。胸部X線検査では、気管支透亮像(エアブロンコグラム)を伴う浸潤陰影がみられます。
間質性陰影はウイルス、マイコプラズマ、クラミジア肺炎にしばしばみられ、すりガラス、網状、粒状陰影を示します。
ウイルス性肺炎では異形リンパ球の出現がみられ、マイコプラズマ肺炎では抗体価上昇や寒冷凝集反応が上昇します。
膿性痰(うみ状の痰)では細菌感染症が疑われます。できうる限り痰の検査(細菌培養検査、グラム染色)をして、肺炎の原因菌を探します。血清診断(抗体価)以外に、肺炎球菌やレジオネラの尿中抗原検出キットによる迅速診断が可能です。

その他には患者さんからの情報として、鳥(オーム、インコなど)を飼っているか、最近その鳥が死ななかったか、ハトなどと身近に接触していないか、循環型風呂で入浴していないか、症状の出る前に温泉旅行に行かなかったか、などが診断の助けになります。
肺炎の治療
抗菌薬(抗生物質など)による化学療法が主体です。通常は経口抗菌薬で治療しますが、 体力の弱っている高齢者や嘔吐、下痢、食欲不振などがあって体力の低下している患者さんなどでは、しばしば口から薬をのむことができず、逆に食欲不振が増して症状を悪化させることがあるので、 即効性があり確実な抗生物質の経静脈投与(血管注射)が主体となります。
基本的には外来での通院治療が可能ですが、入院治療するかどうかは、成人市中肺炎診療ガイドライン2007が採用する重症度判定システム、
A=DROPスコア(Age、Dehydration、Respiratory failure、Orientation disturbance、shock blood Pressure:年齢、脱水、呼吸不全、意識障害、血圧)などを参考に、
どんな基礎疾患があるか、通院可能か、食事ができるか、心不全がないか、全身状態がどうかなどを総合的に判断して決定することになります。
| 化学療法 |
|---|
| 治療する所が外来と決定されたなら、成人市中肺炎診療ガイドライン2007に沿って、まず細菌性肺炎か非定形肺炎かを判断します。 |
細菌性肺炎
|
非定型肺炎
|
| 一般療法、補助療法 |
|---|
| 全身の栄養状態の改善、痰が出にくい時の吸入療法、脱水に対する処置、低酸素血症に対する酸素療法などが必要です。入院のうえ人工呼吸管理を必要とする場合もあります。 |
肺炎の注意点
基本的には、インフルエンザ流行期の注意点と同じです。外から帰った後は、よく石鹸で手を洗い、うがいをして罹患を防ぎます。
肺炎球菌に対してはワクチン(ニューモバックス)が有効ですので、基礎疾患を持っている方や、高齢の方は積極的に受けることが望ましいです。榎本医院では肺炎球菌ワクチンを接種しています。(予約制)
一般的には、後遺症を残すようなひどい肺炎はまれです。熱があり、咳がひどく、痰がきれないなどの症状があるときなどは、すぐに受診しご相談ください。

榎本医院 概要
- 院長
- 榎本 真也 医学博士
- 前院長
- 榎本 哲 医学博士
- 標榜科目
- 内科、脳神経外科、呼吸器内科、小児科
- 医師数
- 2名
- 資格
- 日本内科学会認定医、日本脳神経外科学会専門医
日本救急学会認定専門医、日本脳卒中学会認定専門医
日本脳神経血管内治療学会認定専門医 - 住所
- 〒362-0067 埼玉県上尾市中分1-28-7
- 電話
- 048-725-1651
- アクセス
- JR上尾駅、北上尾駅より車で10分・駐車場17台
診療時間・休診日
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 ~12:00 |
● | ● | △ 第一水曜 |
● | ● | ● | 休 |
| 15:00 ~18:00 |
● | ● | 休 | ● | ● | 休 | 休 |
- 外来休診日
- 第一水曜日、土曜日午後、日曜・祝祭日
- △第一を除く水曜は午前中診療